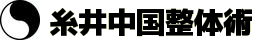【参考程度に】コロナ禍での花粉症対策について
2021/02/01
コロナ禍での花粉の季節がやってきますね。
私は、スギ、ヒノキは大丈夫なんですが、5月頃からのカモガヤなどのイネ科の花粉にやられてしまいます。
ニュースを見てると「花粉症です」と書いてある缶バッジの売上が伸びているとか。
コロナと花粉症の症状が似ているので、誤解されないためには良いアイテムかなと思いました。
さて、今月は参考になればと思い、花粉症対策について書いていきますね。
今年の花粉飛散量は、過去10年の平均飛散量と比較すると、東日本では多く、西日本では例年と同じかやや少なくなると予想されています。
花粉飛散量が少なかった昨年と比較すると、東北南部から関東、東海は2〜4倍、その他の地域は1.2〜2.8倍になるという予想がされているので、油断せずに早めの対策を心がけたほうが良いでしょう。花粉症で困る症状といえば鼻水、鼻づまり、眼のかゆみですよね。
残念ながら花粉症の症状を完全に抑える薬はありません。
症状を軽減させる方法として、薬を使った免疫療法や鼻の粘膜をレーザーで焼くレーザー治療もあります。
しかし、レーザー治療は症状を緩和させる治療法で完治はしないですし、体質を改善するものでもないので、粘膜が回復することで再び花粉症の症状が出てきます。
マスクやメガネの着用で花粉を100%防ぐことはできません。ある程度、鼻や眼の粘膜に付着してしまうので、洗い流すのが良いでしょう。
鼻の洗浄にはドラッグストアで販売されている鼻うがい専用液があります。眼の洗浄には、近年、水道水で洗眼することは眼を守る役割を持つ涙まで洗い流してしまうため良くないと言われています。なので、洗眼薬を使うことがすすめられています。鼻うがい洗浄液を自分で作る場合は、35〜37℃の人肌くらいまで温めた水道水に、0.9%の食塩水(1リットルの水に対して9グラムの食塩を溶かす)を作ります。その食塩水を、先が細いボトルなどで鼻の奥に流し込むと、鼻うがいができます。くれぐれも水道水を鼻に流し込まないようにしてください。体液と水道水の浸透圧が違うので、鼻の奥がたまらないくらいツーンと痛くなってしまうので気をつけてください。
次に、鼻に効くツボの一部をご紹介します。
鼻水、鼻づまりに即効性のあるツボは、やはり鼻のまわりにあります。
小鼻の最もでっぱったところのつけ根に、迎香(げいこう)というツボがあります。軽めの症状の場合はここで鼻が通ります。しかし、迎香を押しても症状が治まらないことが多いと思います。
そんな時は迎香の上、小鼻のつけ根の両脇にある、天迎香(てんげいこう)というツボを押してみてください。
このツボは効果が高く繊細なので、強く押さずに、そっと押さえるくらいの刺激でとどめておくのがベストです。花粉症の方は痛みがありますが、押すことで鼻が通るようになってきます。
ツボの押し方は、両手の人差し指の腹で、斜め45度の角度で上に向かって押し、押す時間は1回に20秒くらい、長くて2分以内ですが、症状が治まった時点で押すことを中止してください。
そしてまた、症状が出てきた時に押すようにしてください。
あと、栄養面で改善していく方法をご紹介します。
花粉症は免疫機能の異常(アレルギー反応)なので、からだの免疫力を高めることで抵抗力が上がり、アレルギー反応を抑えることが期待できます。
つまり、免疫機能が正常に働いていると、花粉症特有のアレルギー症状は抑えられるということです。
免疫細胞は約60%が腸に集中しているので、腸内環境を整えることが正常な免疫機能の活動につながっていきます。
その免疫力を高めていくために、普段から取り入れたい食べ物として2種類あります。
ひとつめは乳酸菌です。
ヨーグルト、チーズ、味噌、キムチなどの発酵食品を取り入れてみてください。
乳酸菌は腸内環境を整えるうえに、免疫細胞のバランスを整える働きもあります。
私は普段からヨーグルトを摂るようになってから花粉症が緩和しました。去年は特にそう感じましたね。それまでは、きつめの薬を飲んでいましたが、去年から軽めの薬とヨーグルトで症状は緩和されたので、試してみようと思う方は試してみてください。ヨーグルトの種類は普通の安いヨーグルトです(^^)
ただし、即効性のあるものではありません。あくまでも予防食品ですし、日々の積み重ねが大事です。
ふたつめは食物繊維です。
免疫力を高めるためには、乳酸菌などの善玉菌のエサになる食物繊維を摂ることも大事です。
腸内環境を整えるほか、善玉菌の増加を促します。
善玉菌の増加は、花粉の吸収を抑える抗体の増加にもなるので、食物繊維を積極的に摂ることで花粉症の症状を抑えることにつながります。
最後に、鼻水が出るときにやりがちな行為には気をつけてください。まず、鼻のかみ方です。
鼻水が多かったりすると、鼻を勢いよくかんでしまいがちです。ところが、勢いよくかんでしまうと症状がより悪化することもあります。
鼻の粘膜が腫れることで鼻水が増えたり、鼻がつまりやすくなったりしますが、そんな状態で激しくかんでしまうと炎症が悪化してしまいます。逆に鼻水をすすっていると、鼻と耳のつながる管を通じて、耳の内部に粘液や細菌が逆流して炎症を起こすこともあります。そんなことにならないように、鼻をかむときには、片方ずつ静かにかむようにしてください。
鼻を勢いよくかむと、高い圧力で空気の摩擦が起こり、炎症部分がこすれて腫れがひどくなるリスクがあるからです。
あと、男の子がやりそうなことですが、鼻にティッシュを詰める行為です。
鼻水がツライと、つい鼻にティッシュを詰めたくなりますよね。
鼻水の中にはアレルギー反応によってできた化学物質がたくさん存在しています。ティッシュで詰めておくと、鼻の中が慢性的に腫れた状態になってしまいます。さらには、自然に口呼吸になってしまうので、鼻の粘膜と喉には良くないので、ティッシュを鼻に詰めるのはやめておきましょう。
今月も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
関連エントリー
-
 ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
-
 股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
-
 膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
-
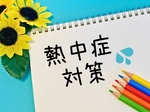 アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
-
 インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
糸井中国整体術
当院は完全予約制です。夜9時からの施術や土曜、日曜、祝日のご予約、施術もご相談ください。
| ご予約・お問合せ お客様専用電話番号 | 090-1148-5583(2代目院長直通) |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町18-2 |
| 電話予約受付時間 | 9:00〜22:00 営業のアポ取り、事業提案等の営業行為の類いは一切受付けていません。 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00が基本ですが、時間外でも可能な限り対応させていただきますので、 遠慮なくご相談ください。 |
| 定休日 | 不定休 |
| 2代目院長 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | 要相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |