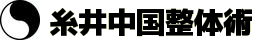- ホーム
- ブログ
ブログ
【参考程度に】コロナ禍での花粉症対策について
2021/02/01
今年の花粉飛散量は、過去10年の平均飛散量と比較すると、東日本では多く、西日本では例年と同じかやや少なくなると予想されています。
花粉飛散量が少なかった昨年と比較すると、東北南部から関東、東海は2〜4倍、その他の地域は1.2〜2.8倍になるという予想がされているので、油断せずに早めの対策を心がけたほうが良いでしょう。
まさか便秘が?
お腹の緊張が高いことで腰痛の原因になることもあるんです!
2021/01/01

お酢を摂るとからだは柔らかくなるの?
2020/12/01
体が硬い人には気になる話だと思いますが、結論から言うと残念ながら、お酢を摂ってもからだは柔らかくなりません(>_<)
科学的な根拠もありません。毎日たくさんの種類のストレッチをしても継続できなければ、からだの柔らかさは得られません。
1種目だけでも毎日お風呂あがりに30秒すると決めて、ハードルを下げて継続するほうが間違いなく早く柔軟性は得られます。
時間に余裕がある日は種目を増やしたり、時間をいつもよりかけたりすることで、からだを柔らかくする目標は達成しやすくなってきます。初めから高い目標を決めてしまうと続かなくなるので、お風呂上がりの体が温まっている30分以内に20〜30秒を目安にやってみてください。
では、お酢はからだにどんな影響を与えるのでしょうか?
お酢の主成分である酢酸は体内に入るとクエン酸に変化します。クエン酸には血管の拡張や血行の改善、疲労回復をより早める効果があります。
いままでの説では、疲労物質である乳酸が溜まることで筋肉が硬くなり、そのぶん柔軟性は落ちるので、お酢を摂ることで「乳酸」を取り除き、筋肉の凝りや緊張、張りといった症状を改善する働きがあると言われていました。つまり、「もともと持っている柔軟性を回復させる」という意味では、「お酢がからだを柔らかくする」というふうに解釈もできます。
しかし近年、乳酸が疲労の直接的な原因ではないことが明らかにされてきており、むしろ、乳酸は私たちのからだにとってプラスの働きをするエネルギー源であることがわかってきています。
お酢の摂取は、直接的に関節や筋肉を柔らかくすることにはつながりませんが、疲労の回復を促進してくれるもので、健康によいものであることは間違いありません。
あなたが持つ本来の自然治癒力を発揮できる状況を作り出してくれるので、うまく活用していくようにしたいものですね。お酢の摂り方には少々注意が必要です。
まだ知らない方は驚愕するかもしれない内容です。
2020/11/01
関節矯正といえば、関節をポキポキ鳴らすというイメージを持つ方がほとんどでしょう。
関節が鳴ることで、関節のズレが治った!と思っている方がたくさんいらっしゃいます。
からだが整ってスッキリ爽快感!と感じる方や、逆にこの音に恐怖心を持たれる方もいらっしゃいます。
私の考えは、症状が消えれば、どんな施術方法でも良いと思っています。
ただ、上記のように関節を鳴らすことで関節のズレが治るという誤解をされていてはいけないと思い、気のついたことを2つ訂正するべく、正しい認識と私の施術方針知っていただきたい思いで、今月はこのようなブログを書きました。
誤解その1:関節を矯正して音が鳴ったから、関節のズレが治った音ではありません
先月のブログにも書きましたが、関節を矯正してポキッと音が鳴るのは関節内の気泡がはじけた音で、関節のズレが治った音ではありません。
関節を鳴らす=関節のズレが治るという目的で父は施術をしていたので、よくポキポキと鳴らす施術をしていました。
関節のズレの原因は筋、筋膜などの軟部組織の硬さが関係しています。
関節を無理に鳴らそうとする行為が危険なんです。
父が引退したので言わせてもらいますが、父の施術は少々強引にでも関節を鳴らそうとするタイプの施術でした。
私に代が変わってからは、お客様に「じつは矯正されるのが怖かったんやけど、言えなくて我慢してた」というような話をカミングアウトしてくださった方がたくさんいらっしゃいます。
たしかに、無理に鳴らそうとするあまり、関節の可動範囲を超えて圧力を加えたり、お客様の身構えを無視してグイッと関節を鳴らそうとすることで筋肉や靱帯を痛めてしまうことがあります。他にも、YouTubeでみたことがあるのですが、タオルを首の後ろに引っかけて、ものすごい勢いで首を引っ張り、勢いがついているのでからだも一緒に引っ張られた方向に移動してしまっている施術を見たことがあります。あれは完全に筋繊維や靱帯を痛めてしまいやすいやり方で非常に危険な施術だなと思ったことがあります。
また、関節を鳴らす整体は非常に悪いと書いているのも見かけますが、関節を鳴らす整体が悪いのではなく、やり方や目的の問題だと私は思っています。
誤解その2:1回で治るという言葉の魅力 施術の回数で症状を治していくのではありません
もうひとつは、症状が1回で治るです。
まとめ
●関節を鳴らすから関節のズレが治ったのではありません。関節が鳴らないから関節のズレが治っていないのではありません。
●私2代目の施術は、筋肉などの軟部組織の硬さが原因で関節のズレが生じて様々な症状が現れるため、軟部組織を収縮させる、伸ばす、押圧する方法で関節のズレを治す。
関節がポキポキ鳴る音の正体とは?
2020/10/01
呼吸の仕方に気を止めたことありますか?
腹式呼吸と胸式呼吸の違いは?
2020/09/01

腹式呼吸は、ざっくり言うとお腹を膨らませて呼吸するイメージを持つ方が多いと思います。細かく言うと、横隔膜の動きを意識した呼吸が腹式呼吸といい、ヨガの呼吸法で使われています。
横隔膜は、肺の底にある伸縮性の高い筋肉の膜のことです。この横隔膜が上下に動くことで肺に空気を取り込んだり、吐き出したりするのが腹式呼吸です。
横隔膜を意識して使うと、横隔膜の動く範囲は広がっていくので、結果として肺への酸素供給と吐き出す力は自然に強くなって鍛えられていきます。胸式呼吸は胸周辺が動く呼吸法で、ピラティスの呼吸法で使われています。
胸式は肋骨の間にある肋間筋という筋肉が動きます。肋骨はからだの上方に動きやすく、胸腔が広がることで空気を取り込みやすい状態になるので、胸式呼吸は息を吸うことに向いています。腹式と胸式の見分け方は、深く息を吸おうとしたときに、肩が上がっているかどうかです。
腹式の時は、肺の下にある横隔膜が上下をしているので、お腹が膨らんだりへこんだりするだけで肩まではあがりません。
運動しているときの呼吸は、酸素をたくさん取り込むのに胸だけで行っているので、肩も一緒に上がるため胸式呼吸になります。腹式、胸式呼吸のメリットは、息を吐ききり、大きく吸うことで肺の中は新鮮な空気でいっぱいになることで心肺機能と血行が良くなります。
腹式にしても胸式にしても、深い呼吸を行うことで、交感神経、副交感神経のバランスを取りながら心身を健やかな状態になることは共通しています。
今年の夏は特に気をつけたい熱中症対策
2020/08/01
ひょっとしたら、呼吸が浅いかも?
浅い呼吸がもたらすものとは?
2020/07/01

ストレッチをするのはいつがいいの?
効果を出すにはコレ!
2020/06/01

湯船に浸かって(37〜39℃の微温浴がベスト)からだの芯から温めることで、疲労で硬くなった筋肉はゆるみ、お風呂から上がってからストレッチをすると筋肉は伸びやすくなっています。
お風呂から上がって何分後にするのが良いか気になりますよね?
女性ならお風呂から上がって髪を乾かしたり、身支度していると20〜30分はかかるでしょう。
【 新型コロナから身を守ろう! 】食事で免疫力をUP!
我が家で気をつけている食事をご紹介
2020/05/01

-
 ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
-
 股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
-
 膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
-
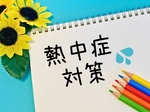 アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
-
 インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
糸井中国整体術
当院は完全予約制です。夜9時からの施術や土曜、日曜、祝日のご予約、施術もご相談ください。
| ご予約・お問合せ お客様専用電話番号 | 090-1148-5583(2代目院長直通) |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町18-2 |
| 電話予約受付時間 | 9:00〜22:00 営業のアポ取り、事業提案等の営業行為の類いは一切受付けていません。 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00が基本ですが、時間外でも可能な限り対応させていただきますので、 遠慮なくご相談ください。 |
| 定休日 | 不定休 |
| 2代目院長 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | 要相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |